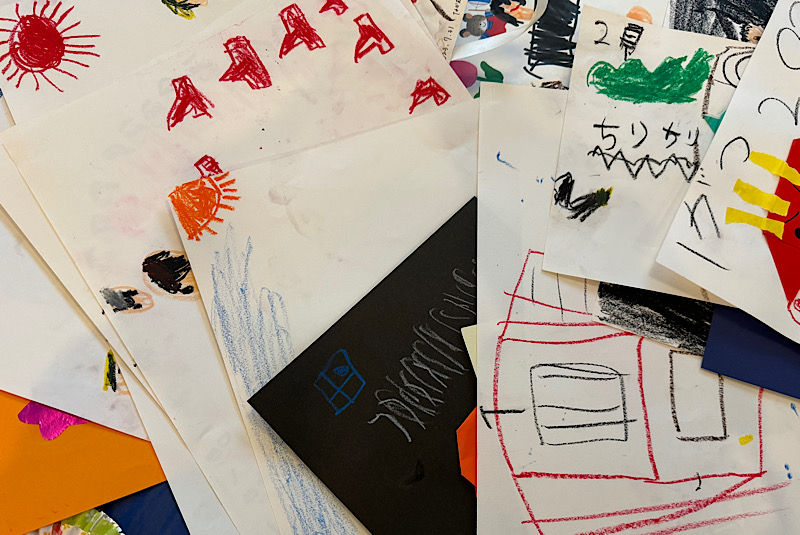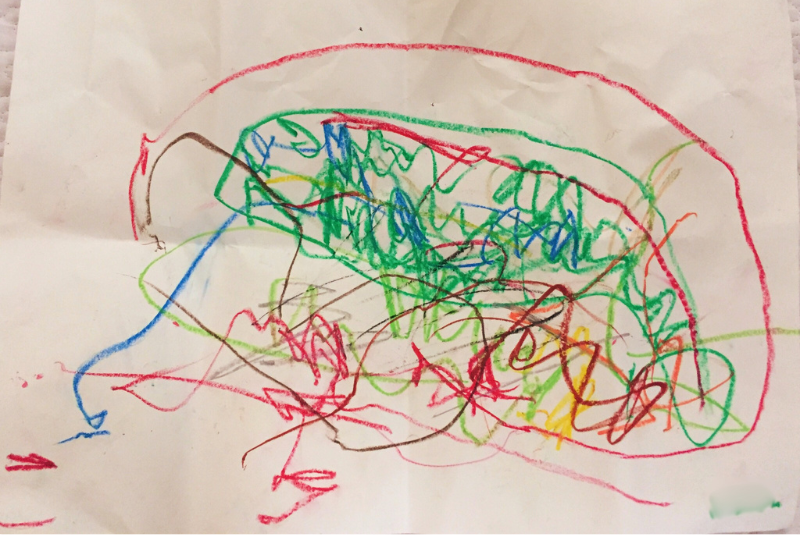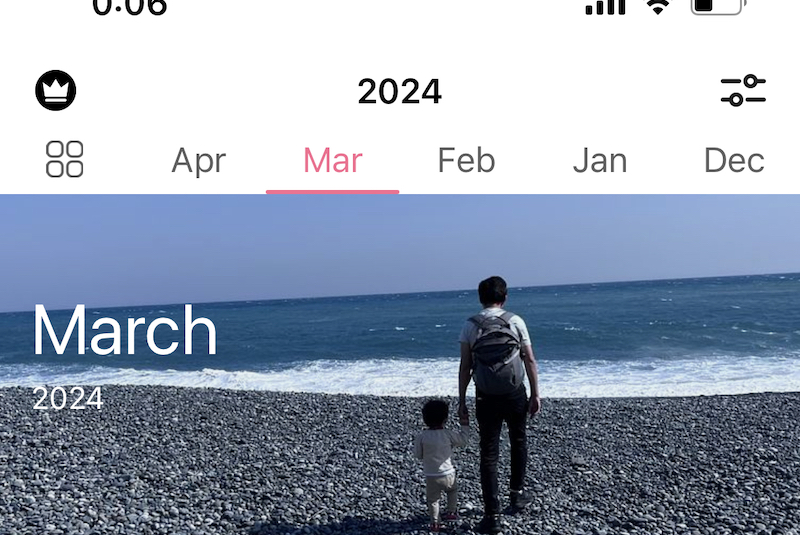大雨・台風で想定される被害
1)洪水
大雨などにより、河川の水位が著しく上昇し、堤防から水があふれたり、堤防が決壊したりする状況をいいます。大量の水が一気に流れ出し、河川の近くの住宅はわずかな時間で浸水や倒壊の危険性があり、さらに人的被害が起こりやすくなります。★しほママコメント★
「洪水は一級河川のような大きな川だけでなく、小さな川でも起こります。これによって周辺の地面よりも低くなっている道路に水が溜まり、車両が水没し死亡例も出ています。乳幼児がいると車移動がラクと思われがちですが、大雨時は危険も伴うことを知っておきましょう。
また、雨水が排水できなくなり、マンホールや側溝、排水路などから水が溢れる内水氾濫にも気をつけて!」
2)集中豪雨・竜巻・落雷
発達した積乱雲によって、同じような場所で数時間にわたり強く雨が降る集中豪雨や、積乱雲が線状に並んだかたまりの線状降水帯、さらに竜巻、突風、落雷などが発生することがあります。★しほママコメント★
「熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した令和2月7月豪雨では線状降水帯が起き、室内でも恐怖を感じる激しい雨が降りました。キャンプや川遊びなど、屋外で長時間過ごすときは気象情報をこまめに確認しましょう。
特に日差しが強い夏は積乱雲ができやすいので、『真っ黒い雲が近づき周囲が暗くなる』『冷たい風が吹く』『大粒の雨やひょうが降りだす』などの変化に要注意! 積乱雲が近づいてきたら、丈夫な建物などにしばらく避難するのが鉄則です」
3)暴風による災害
風が強くなると、物が飛ばされたり、電信柱が倒れたりするなどの被害が起こります。風速15m/sで取り付けの悪い看板が飛ぶことがあり、風速25m/sで屋根瓦が飛ばされたり、樹木が折れたりします。風速30m/sになると、立っていられないほどの風の強さとなり、雨戸や屋根が飛ばされることも。なお、並みの台風で風速25~33m/s未満、非常に強い台風になると風速45~55m/s未満になります。★しほママコメント★
「対策は風が吹く前に行いましょう。植木鉢や自転車など、飛ばされそうなものは台風が接近する前に固定したり移動させたりすることが大切です」
4)停電
台風の時は倒木による電柱の倒壊や飛来物による送電線の切断、落雷による送電線の損傷によって、停電が起こることがあります。★しほママコメント★
「台風や集中豪雨が起こりやすい夏から秋にかけての暑い時期の停電で心配なのが熱中症です。赤ちゃんは体が小さく体温調節がうまくできないので、特に注意してあげてください。母乳やミルクでしっかり水分補給することはもちろんのこと、濡れタオルやうちわなどで暑さをやわらげましょう。冷凍庫に保冷剤を常備しておくことも対策になります」
◆がけ下や山すそに住んでいる人は土砂災害に注意!
土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂災害は、地震のみならず集中豪雨や台風の大雨が引き金となって起こることが多く、すさまじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの人命や住宅を奪ってしまう恐ろしい災害です。土砂災害警戒区域などに住んでいる場合は、暴風で屋外を移動できなくなる前に早めの立退き避難をしましょう。
◆海のそばに住んでいる人は高潮に注意!
台風や低気圧の接近に伴って、海面の高さが通常よりも著しく高くなる現象をいいます。これによって海水が防潮堤を超えて一気に流れ込んでくると、木造家屋や車などが流されたり倒壊する場合も。高潮災害発生の危険が迫っているときには、避難情報を随時確認し、暴風警報が発表された時点で避難を開始しましょう。
大雨・台風による災害から子どもを守るポイント
1)住んでいる地域のハザードマップを確認しておく
災害発生時に迅速かつ的確に避難を行うためにも、ハザードマップで危険箇所を確認しておきましょう。たとえば、国土交通省の「重ねるハザードマップ」 は洪水浸水想定区域や土砂災害区域、避難所など、災害リスクや役立つ情報を地図上で重ねて確認できるなど、大変便利です。保育園や幼稚園の送り迎えに使う道など、よく通る道などもチェックしておくといいでしょう。★しほママから+αアドバイス★
「ハザードマップには載ってない危険箇所があるのを知っていますか? 大雨で道路が冠水すると、ガードレール、側溝、用水路、マンホール、田んぼのようにまわりより低くなっている所など、普段危険を感じない場所が突然危険な場所に変わります。水圧で開いてしまったマンホールに転落すると、命の危険に関わります。もし冠水したら?という目線で歩く“防災さんぽ”をしてみるのもおすすめです」
2)雨が降り出したら「キキクル」を見よう
大雨による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを、スマートフォンなどでリアルタイムに視覚的に知ることができる情報が気象庁の「キキクル(危険度分布)」 です。大雨による土砂災害の危険度は「土砂キキクル」、短時間の強雨による浸水害の危険度は「浸水キキクル」、河川の洪水災害の危険度は「洪水キキクル」で、災害が起こる危険度をマップ上の「色」で確認できます。危険度は10分ごとに更新され、数時間先まで予測されるため、今いる場所からの避難先の必要性を判断するのに役立ちます。
★しほママから+αアドバイス★
「「洪水キキクル」は大河川だけでなく、中小河川も確認できます。中小河川は短時間のうちに急激に水位上昇が起きやすいので注意! 災害リスクのある地域に住んでいる人は、スマートフォンなどに自動で通知がくる、プッシュ型通知サービスを登録しておくと、仕事や育児中でも早めに危険度を知ることができて安心です。情報は命綱になるため、スマホの充電も忘れずにしておいてください」
3)「警戒レベル3」で乳幼児は避難するべし
避難行動や避難のタイミングがすぐに理解できるように、市町村が5段階の「警戒レベル」を用いて伝えています。妊産婦、乳幼児など避難に時間のかかる人は、「警戒レベル3」で避難を行います。なお、各種情報は警戒レベル1〜5の順番で発表されるとは限らないので、気象庁や都道府県が発表する防災気象情報や「警戒レベル相当情報」も参考にしましょう。暗い中の避難は、乳幼児連れには危険がいっぱいです。明るいうちに避難を済ませておきましょう
★しほママから+αアドバイス★
「出がけにうんちをしてしまった、ぐずってしまい支度が思うように進まないなど、赤ちゃん連れでの避難にプチハプニングはつきものです。出るまでに時間がかかることも想定して、『警戒レベル3』になるまでに避難する準備は整えておきましょう。授乳を済ませておく、ミルクの場合はお湯を水筒に準備しておくことは必須です。
また、家族や友人など、頼れる人に連絡し、避難の場合は協力をあおぐなど、ひとりで抱え込まず、まわりを頼ることも大切です」
大切な命を守るために日頃からできる備え
さらに、内閣府の防災情報のページでは、各自治体防災情報一覧 があるので、お住まいの都道府県の防災サイトも、ぜひ一度チェックしてみましょう。
ただし、都道府県の防災ポータルサイトは情報量も多いため、ほしい情報にたどり着くのに時間がかかることも。お住まいの地域の災害リスクに合わせて必要な情報が書かれたページのURLをスマホのメモに貼り付けておく、リーディングリストに登録しておくなどすると、いざというときに慌てません。
★しほママから+αアドバイス★
「たくさんの防災情報があると何を見たらいいのかわからなくなりますよね。まずは、お住まいの地域の防災サイトをのぞいてみましょう。地域によっては、動画やダウンロードできる役立つ情報などが掲載されていて、見てお得なことがあります。
ただ、忙しいママやパパは自分から情報を取りにいく時間やゆとりがないことも。その場合、通知サービスを登録して、メールやLINEで防災や安全に役立つ情報が自動的に届くようにしておき、スキマ時間で見る習慣をつけておくのもおすすめです。検索サイトで『防災情報メール 世田谷区』など、お住まいの地域で検索してみてください」
*
最後に、しほママからのメッセージをお伝えします。
「私はいつも、『風水害は定期テスト』とお伝えしています。風水害は事前に備え、避難することができる災害だからです。とはいえ、乳幼児がいると、避難準備や行動に時間がかかり、『もう少し様子をみてから』『まだ大丈夫』という気持ちが勝り、なかなか“避難スイッチ”が入りません。
そこで、ママ友やご近所さんと協力して、避難の練習をしてみましょう。一度避難を経験すると、スイッチが入りやすくなりますよ。そして、『水害は逃げるが勝ち!』。この言葉をどうか忘れずに」
文/羽田朋美(Neem Tree )